登録販売者の資格取得に挑戦!60代からでも目指せる新たな一歩【濱西慎一】
こんにちは、濱西慎一です。
これまでの仕事とは異なる分野で新たな知識を身につけることに興味を持ち、さまざまな資格取得に挑戦するのは楽しいものです。でも、どうせなら楽しいだけではなく、生活に役立つ勉強をするのも良いですよね。
そこで思い立ったのが「登録販売者」です。
今回は、一般用医薬品の販売に関わる「登録販売者」の資格について調べてみました。医薬品に関する知識を深めることで、自分自身や家族の健康管理にも役立つのではないかと考えています。
登録販売者はどんな仕事をする人?

登録販売者というのは、ドラッグストアなどで一般用医薬品(いわゆる市販薬)を売るための資格を持った人のことです。ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、実は私たちの身近にいる存在なんです。
たとえば薬剤師が不在の時間帯でも、登録販売者がいれば風邪薬や胃薬といった第2類・第3類の薬を販売することができます。(第1類医薬品は薬剤師によってのみ販売が許可されているので、登録販売者では販売できません)そう聞くと、「あぁ、あの人たちか」とピンとくる方もいるかもしれません。
ただ、薬を棚から出して「はい、どうぞ」と手渡すだけではありません。登録販売者には、薬の使い方や注意点をきちんと説明し、お客さんに安心して使ってもらうという大事な役割があります。
ここからは、そんな登録販売者の主な仕事について、私なりに噛み砕いてお話ししてみます。
一般用医薬品の販売および情報提供
いちばんわかりやすい仕事は、やっぱり薬の販売です。ただし、単にレジでお会計するだけではありません。
お客さんが薬を手に取ったとき、「どういう症状があるのか」「今、他に薬を飲んでいないか」「アレルギーはないか」など、いくつかのポイントを確認する必要があります。実際、こうした会話を交わしている様子を、薬局の店頭で見かけたことがある方も多いと思います。
風邪ひとつとっても、熱が出てる人と、喉が痛い人では選ぶべき薬が違いますよね。登録販売者は、そういった違いをちゃんと見極めたうえで、「これが合いそうですよ」と商品を提案します。まさに“薬選びの案内人”と言える存在です。
顧客への適切なアドバイス
薬は使い方を間違えると、かえって体に悪い影響を及ぼすこともあります。だからこそ、登録販売者は「正しく使ってもらう」ためのアドバイスも欠かせません。
たとえば、「この薬には眠くなる成分が入っているので、車を運転する前には飲まないでくださいね」といった注意はよく聞きますね。あるいは「今ほかの薬を飲んでいるなら、かかりつけのお医者さんに一度相談してみてください」と案内することもあります。
こうした一言で、お客さんの不安がすっと軽くなることもあるんですよね。自分が口にするものだから、安心して選びたい。そんなときに頼りになるのが登録販売者、というわけです。
医薬品の在庫管理と発注業務
店頭に並ぶ薬たちは、当然ながらずっと棚に置きっぱなしというわけにはいきません。薬は期限があるものですし、売れ筋や季節によっても動きが変わります。春や秋口には花粉症の薬のコーナーが大きくなったりしますよね。
登録販売者は、在庫が足りているかをチェックしたり、そろそろ切れそうな商品を発注したりします。逆に、多すぎても期限切れになってしまうので、そのあたりのバランス感覚も大事なんです。
それから、薬は高温や湿気に弱いものも多いので、保管場所の温度や湿度にも注意を払う必要があります。見えないところで、けっこう気を使っているんですね。
店舗での衛生管理や法令遵守の確認
医薬品を扱う以上、法律やルールを守ることも大切です。たとえば、薬は他の商品と混ぜて並べてはいけない決まりがありますし、販売記録もちゃんと残しておかなければなりません。
それに、偽物の薬や、期限が切れてしまった薬がうっかり売られてしまわないよう、常に目を光らせる必要もあります。言ってみれば、店の中で「薬の番人」のような存在でもあるわけです。
薬剤師と登録販売者の違いって?

「登録販売者って、薬剤師とどう違うの?」と疑問に思った方、けっこう多いんじゃないでしょうか。私も最初はよくわかっていなくて、調べながら「なるほど」と思うことがいろいろありました。
一番大きな違いは、扱える薬の種類です。薬剤師は医療用医薬品、つまり病院で処方される薬も含め、すべての医薬品を扱える資格ですが、登録販売者はあくまで一般用医薬品、いわゆる市販薬(第2類・第3類の医薬品)を扱う資格です。
それでも、私たちが普段よく手に取る風邪薬や胃薬、湿布薬などの多くは登録販売者の守備範囲。日常生活に関わる薬がメインなので、知識としても実用的なんです。
また、資格を取るまでの道のりにも大きな差があります。薬剤師は大学で6年間学び、国家試験に合格しなければなりませんが、登録販売者の試験はもっとハードルが低く、年齢や学歴、実務経験などの制限もありません。私のようなシニア世代でも「ちょっとやってみようかな」と思える資格なんです。
ただし、責任の重さはどちらも変わりません。人の体に直接関わる仕事ですから、いい加減な判断は絶対にできません。だからこそ、登録販売者もきちんとした知識と意識が求められるんですね。
薬剤師が“医療のプロフェッショナル”だとすれば、登録販売者は“市販薬の頼れるアドバイザー”。そんなふうに理解すると、両者の役割の違いが見えてくるかもしれません。
登録販売者の資格を取るメリット
登録販売者の資格って、実際のところどんなメリットがあるんだろう?そんなふうに思っている方も多いと思います。私自身、最初は「ちょっと面白そうだから」という軽い気持ちで調べ始めたんですが、知れば知るほど「これは取っておいて損はないな」と感じるようになりました。
まず、なんといっても就職や再就職の場面で強いです。登録販売者は、全国のドラッグストアや調剤薬局、ホームセンターなど、いろんな店舗で必要とされている資格なので、持っているだけで求人の選択肢がぐっと広がります。(※とはいえ、実際に一人前の「登録販売者」と認められるには実務経験がいるそうです)年齢を問わず活躍できるという点も、私、濱西慎一のようなシニア世代には大きな魅力です。
さらに、医薬品の知識が身につくことで、自分や家族の健康管理にも役立ちます。市販薬を選ぶとき、「これはうちの体質に合うかな」といった判断がしやすくなりますし、ちょっとした不調のときにも落ち着いて対応できるようになります。日常生活で使える知識というのは、やっぱり心強いものですね。
登録販売者の資格には、実利だけでなく“気持ちの充実”というメリットもあると私は思っています。
登録販売者の試験について調べてみた

実際に登録販売者になるには、ちゃんと試験に合格しなければなりません。ちょっと尻込みしてしまいそうですが、調べてみると、思ったよりも身近な試験だということがわかってきました。
試験は年に1回、都道府県ごとに行われます。申し込み方法や日程は地域によって違うのですが、だいたい6月〜8月あたりに願書を出して、試験自体は9月前後というところが多いようです。ちなみに年齢制限もありません。
試験は筆記のみで、全部で120問。科目は5つに分かれています。「医薬品の性質」「人体の仕組み」「法律の知識」「薬の種類」「安全な使い方」など、けっこう広い範囲をカバーしています。でも逆に言えば、実務経験がなくても、ちゃんと勉強すれば誰でも受けられるというのは心強いですよね。合格基準は、全体で70%以上の正答率と、各科目ごとに35%以上を取ること。つまり、まんべんなく理解していればOKというわけです。
2024年に東京都で実施された登録販売者試験では、受験者数が4,257人で合格者がそのうちの1,948人。合格率は45.8%でした。
独学でも合格を目指せる人は多いですが、最近は通信講座やアプリも充実しているので、自分に合ったやり方でコツコツ進めるのがよさそうです。
もっと勉強したい人に!関連資格は?
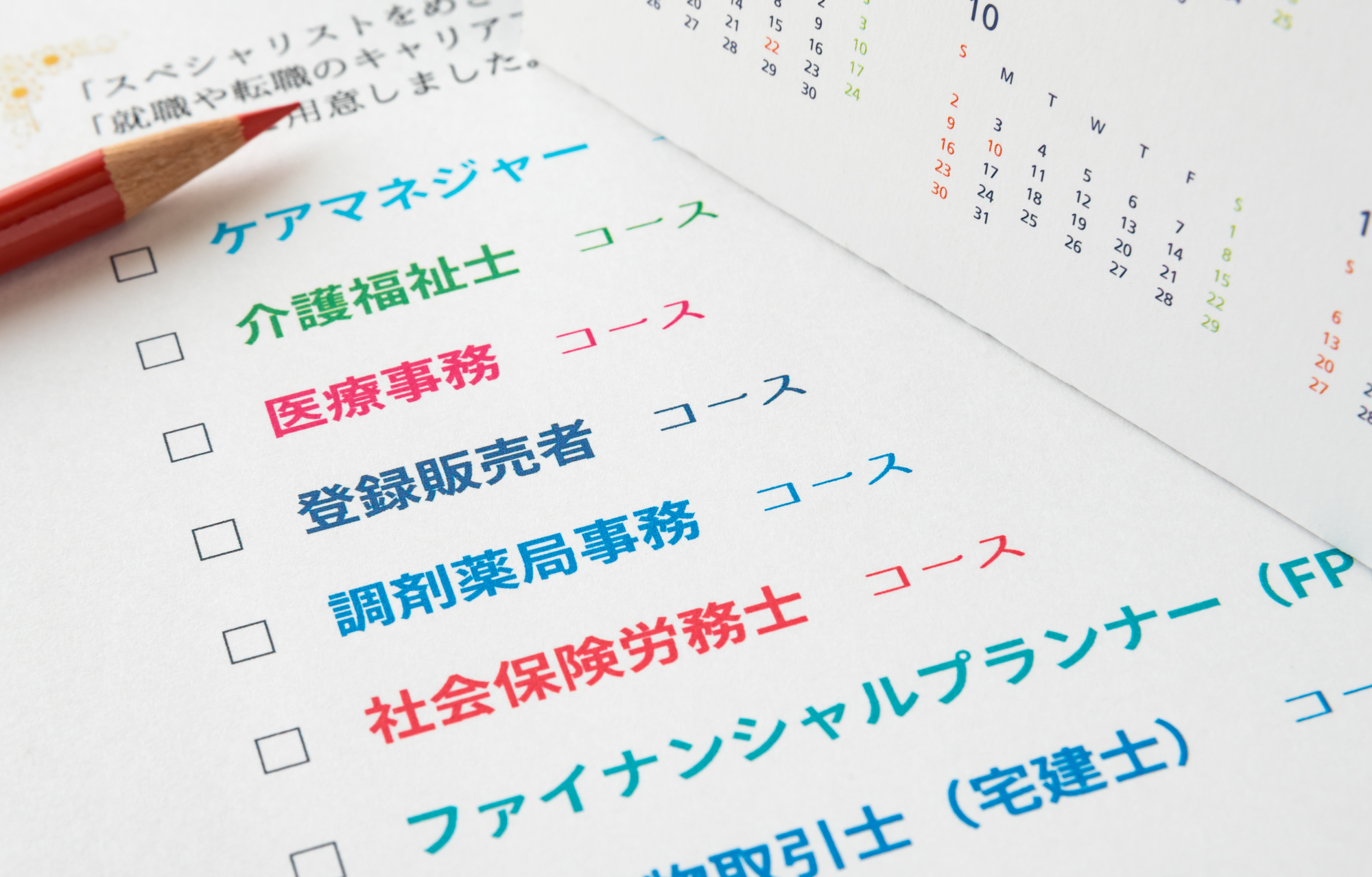
登録販売者の資格を取ったあと、「もっと勉強したいな」と思う方もいると思います。実は、関連する資格もいろいろあるので、そちらも紹介していきたいと思います。
まずは、「リテールマーケティング(販売士)」という資格。名前はちょっと堅いですが、要するにお店の運営や販売のノウハウを学べる資格です。1級から3級まであって、ドラッグストアでのキャリアアップを目指す人にはおすすめとのこと。接客だけでなく、商品管理や売り場作りまで学べるそうです。
それから「医療事務」や「調剤事務」など、事務系の資格もあります。これらを取っておけば、薬局や病院の受付や事務として働く道も開けてきます。登録販売者の知識と組み合わせれば、かなり強力なスキルセットになりますね。
今はオンラインで学べる講座も多いので、自分のペースで勉強できるのがうれしいところです。私と同世代のみなさんも「もう歳だから」とは思わず、興味があるならぜひチャレンジしてみる価値はあると思います。
まとめ
登録販売者は、医薬品に関する知識を活かして人の役に立てる仕事です。60代からでも目指せる資格で、試験も年1回とチャンスがあります。勉強範囲は広いものの、実務経験がなくても受験できるのは本当にありがたく思う人も多いんじゃないでしょうか。
実際に受験するかどうかは別として、こうして調べたり、勉強を始めたりするだけでも、日常生活での意識が変わってきます。「この薬、なんでこんな注意書きがあるんだろう」とか、「あの棚の商品、前と成分が違うな」とか、そういった小さな気づきが増えるんですよね。
これから先の人生、「学ぶこと」をやめたくない。そんな思いで、私はこの登録販売者という資格にも挑戦してみようと思っています。